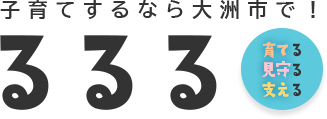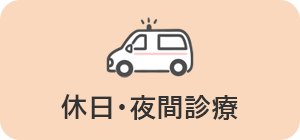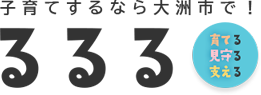本文
出産育児一時金の支給
国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以上あれば、在胎週数22週未満(死産・流産)の場合にも出産育児一時金が支給されます。
支給額は、出産日や医療機関の産科医療補償制度加入の有無などの条件によって変わります。詳しくは以下の表をご確認ください。
| 出産日 | 産科医療補償制度に加入している場合 |
産科医療保障制度に加入していない場合 または、妊娠12週以上かつ在胎週数22週未満の出産の場合 |
|---|---|---|
| 令和5年4月1日以降 | 50万円 | 48万8千円 |
| 令和5年3月31日以前 | 42万円 | 40万8千円 |
なお、会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)。健康保険によっては、独自の付加給付を行っているため国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。
支給方法は、次の2通りとなります。
(1)直接支払制度を利用する
直接支払制度とは、市が医療機関(病院)に出産育児一時金の支給額(※)を上限とし、直接出産費用を支払う制度のことです。
この制度を利用するためには、医療機関(病院)が世帯主の代わりに出産育児一時金を受け取ることに同意が必要ですので、受診している医療機関(病院)へお問い合わせください。
この場合、出産育児一時金は、市から審査支払機関(国民健康保険団体連合会)を通じて、医療機関に支払われます。
出産費用によっては手続きが必要になる場合がございますので、次の項目をご確認ください。
【出産費用が出産育児一時金の支給額(※)を上回った場合】
差額分を医療機関にお支払いください。
例:出産費用が53万円、産科医療補償制度に加入している医療機関で令和6年3月に出産の場合
53万円(出産費用)-50万円(支給額)=3万円
医療機関へ差額の3万円をお支払いください。
【出産費用が出産育児一時金の支給額(※)を下回った場合】
差額分を世帯主が受け取れます。
例:出産費用が45万円、産科医療補償制度に加入している医療機関で令和6年3月に出産の場合
50万円(支給額)-45万円(出産費用)=5万円
5万円を世帯主へ支給することができます。
以下のものを持って市役所窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 世帯主名義の預貯金通帳(または口座番号等の分かるもの)
- 出産したことが分かる母子健康手帳または医師の証明書
- 医療機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
- 医療機関で発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)
(2)世帯主が直接受け取る
(1)の直接支払制度を利用せず、医療機関で出産費用の全額を支払った場合は、出産後、以下のものを持って市役所窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 世帯主名義の預貯金通帳(または口座番号等の分かるもの)
- 出産したことが分かる母子健康手帳または医師の証明書
- 医療機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
- 医療機関で発行される「直接支払制度」を利用しない旨の書類
申請窓口及び問合せ先
本 庁 市民課国保係
Tel (0893)24-1713
長浜支所
Tel (0893)52-1113
肱川支所
Tel (0893)34-2311
河辺支所
Tel (0893)39-2111
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)