本文
要介護(要支援)認定について
介護サービスを利用できる人
年齢によって介護保険サービスを利用できる条件が異なります
65歳以上の人(第1号被保険者)
介護や支援が必要となった理由にかかわらず、保険者(大洲市)から、介護または支援が必要と認定された人
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
次に掲げる16の特定疾病が原因で要介護・要支援状態となり、保険者(大洲市)から、介護または支援が必要と認定された人
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
要介護(要支援)認定の申請
介護保険サービスを受けるためには、大洲市高齢福祉課に要介護認定申請を行います。申請手数料はかかりません。
まず、本人または家族が高齢福祉課または地域包括支援センターに相談してみましょう。
指定居宅介護支援事業所などに代行してもらうこともできます。
申請の代行ができる人
- 指定居宅介護支援事業所
- 地域包括支援センター
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 成年後見人
- 民生委員
- 介護相談員
申請時に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 被保険者本人および申請者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など
顔写真入りの本人確認書類が無い場合は、健康保険の被保険者証や年金証書など2点以上 - 第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)の場合は、健康保険の加入情報が分かるもの
第2号被保険者は医療保険情報の確認が必要です。詳しくは下記のページをご確認ください。
第2号被保険者の要介護・要支援認定における「医療保険情報の確認方法」について
要介護・要支援認定申請書の様式
【Word版】介護保険要介護認定・要支援認定申請書 [Wordファイル/33KB]
【PDF版】介護保険要介護認定・要支援認定申請書 [PDFファイル/241KB]
【記入時の注意】介護保険要介護認定・要支援認定申請書 [PDFファイル/297KB]
申請から認定までの流れ
公平・公正な判定を行うため、訪問調査結果などを全国共通の判定ソフトでコンピュータ処理します。(一次判定)
大洲市介護認定審査会において、一次判定の結果と訪問調査の特記事項、主治医意見書を総合的に審査し、要介護度を決定します。(二次判定)
介護認定審査会の判定に基づき、本人に結果通知と被保険者証・負担割合証の交付を行います。
訪問調査
認定調査員(市の職員等)が自宅などを訪問して調査を行います。調査の費用はかかりません。
訪問調査の内容
- 74項目の基本調査(身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応、特別な医療)
- 概況調査(現在受けているサービス、頻度、主訴、家族の状況、家庭環境等)
- 特記事項(具体的な状況など)
主治医意見書
大洲市からの依頼で、申請書に記載された主治医が介護の視点から傷病・医療・状態などの意見を記入します。
介護認定審査会
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されており、一次判定の結果と認定調査の特記事項、主事意見書を合わせて総合的に審査し、要介護度の判定を行っています。
認定結果の通知
要介護度の判定後、本人に結果通知書と要介護度が記載された被保険者証(オレンジ色)、負担割合証(黄色)が交付されます。
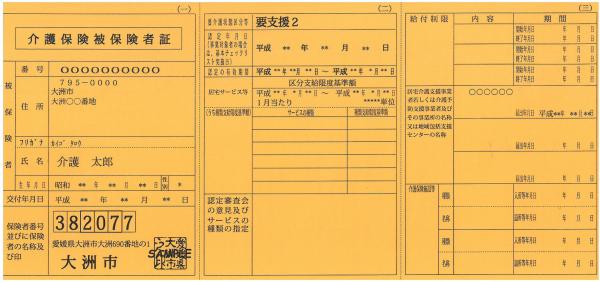
(被保険者証は3つに折って使用します)
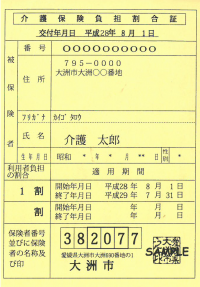
この被保険者証と負担割合証は、介護サービスを利用するときに必要になりますので、大切に保管しましょう。
判定の結果、非該当となった場合は、その結果が通知されます。
要介護度の目安
|
要介護状態区分 |
心身の状態の例 |
|---|---|
| 要支援1 |
|
| 要支援2 |
|
| 要介護1 |
|
| 要介護2 |
|
| 要介護3 |
|
| 要介護4 |
|
| 要介護5 |
|


